- マニュアルは重要なのか?
- マニュアルのメリットにはどういったものがあるのか?
- マニュアルはどうやって作ればいいのか?
この記事は上記のような疑問を抱かれている方に向けて、マニュアルの概要や重要性、メリットを踏まえつつ、作り方を解説します。
マニュアル作成や運用におけるポイントもご紹介しているため、ぜひ最後までご確認ください。
マニュアルの概要
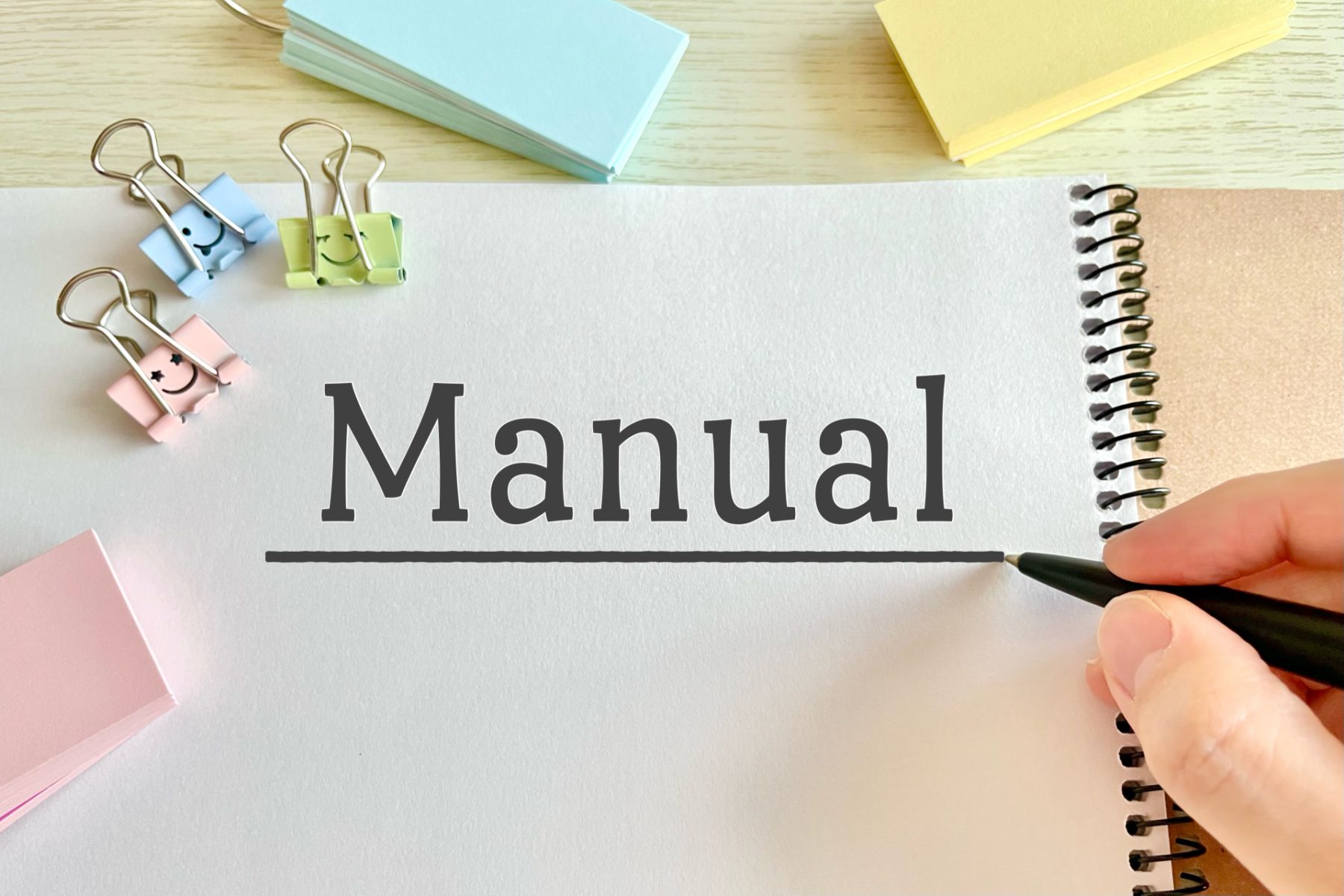
まずはマニュアルの概要や主な種類について確認しましょう。
マニュアルとは
マニュアルとは、業務や作業の手順などを解説したドキュメントです。
マニュアルには具体的な手順は勿論、注意すべき事項などが細かく記載されており、参照することで経験の浅い従業員であってもベテランと同じように業務に従事できます。
また業務全般の目的や意図、背景などを示す上でも役立つツールであり、単純な業務説明書以上の役割を持つと言えるでしょう。
マニュアルの主な種類
マニュアルと一口に言っても様々な種類があります。具体的には以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 業務マニュアル:業務手順や注意点を解説する
- 操作マニュアル:設備や機材の取り扱い、操作方法を解説する
- 規範マニュアル:企業の行動規範や指針などのルールを解説する
- 研修マニュアル:従業員研修を実施する際の内容やルールを解説する
- 接客マニュアル:接客におけるルールやポイントを解説する
このように企業においては様々なマニュアルが作成・活用されていますが、この記事では主に業務マニュアルを対象として解説を進めます。
マニュアルの重要性とメリット

次にマニュアルの重要性を踏まえた上で、メリットについてご紹介します。
マニュアルを作成することの重要性
マニュアルは業務の属人化を防止し、各従業員に安定した業務パフォーマンスを発揮してもらう上で重要な役割を果たします。
また業務改善を行うには業務実態を把握する必要がありますが、マニュアルによって業務が可視化されていれば、現状把握の手間を省くことができ、速やかに改善施策の検討に入ることが可能です。
加えて、業務に紐づけて自社の大切にしている価値観を解説することで、インナーブランディング(従業員に対するブランド浸透施策)の効果を発揮することも期待できます。
このようにマニュアルは単純に業務遂行を助けるだけでなく、様々な活用方法や効果があり、企業にとって重要なツールの一つとなるでしょう。
マニュアルを作成するメリット
ここでマニュアルを作成するメリットを整理してみましょう。
メリット①:業務を標準化できる
一つ目に挙げられるのは、業務を標準化できるという点です。
マニュアルを用意することによって、従業員全員がそれに基づいて業務を遂行できます。
その結果、業務の属人化や業務品質のばらつきを防ぎ、業務の標準化を実現できるでしょう。
メリット②:業務改善を効率化できる
次に挙げられるのは、業務改善を効率化できるという点です。
マニュアルを作成することで、対象業務の詳細が可視化されます。
業務が可視化されることによって、業務上問題が生じた際に、どこに課題があるのかを把握しやすくなります。
そのため改善策の検討も始めやすく、業務改善の取り組み全体を効率化できるでしょう。
メリット③:従業員教育を標準化・効率化できる
続いて挙げられるのは従業員教育を標準化・効率化できるという点です。
マニュアルに基づいて従業員を指導することで、教育担当者が異なることによる教育内容のばらつきを防ぐことができます。
またマニュアルによって「何を教えるべきか」が明確になっているため、指導内容に迷うことがなくなり、効率的な教育・指導を実現可能です。
メリット④:自律的に業務遂行できる環境を構築できる
自律的に業務遂行できる環境を構築できる点も、メリットとして挙げられます。
マニュアルがなければ、業務上不明点が生じた際、先輩や上司に確認するしか解決方法がありません。
しかしマニュアルを用意しておくことで、業務での不明点や疑問点が生じても、自己解決できる可能性が高まります。
このようにマニュアルの存在は、従業員の自律的な業務遂行を促す効果もあると言えるでしょう。
メリット⑤:業務の引き継ぎがスムーズになる
次にメリットとして挙げられるのは、業務の引き継ぎがスムーズになるという点です。
従業員の退職が生じた際、その業務を誰かが引き継ぐ必要があります。
その際、通常は引き継ぎ書類を用意してもらうことになりますが、マニュアルを事前に作成しておけば、引き継ぎ書類を最小限にすることが可能です。
また急な欠勤が生じた場合の代理担当者も、マニュアルを参照することで、スムーズに業務を代行できるでしょう。
メリット⑥:自社の価値観やビジョンを伝えるツールになる
メリットの最後に挙げられるのは、自社の価値観やビジョンを伝えるツールになるという点です。
マニュアルに自社が大切にしている価値観やビジョンも含めて記載し、それを踏まえた上で業務の成り立ちや手順などを解説することで、価値観などを従業員に伝えることができます。
ただ単に価値観やビジョンだけを伝えるよりも、業務と紐づけて伝えることで、従業員側の理解が深まることが見込まれるでしょう。
マニュアル作成のデメリット
ここまでマニュアル作成のメリットについてご紹介してきましたが、デメリットについても簡単に押さえておきましょう。
まずマニュアルを作成するには相応の工数がかかります。
一度作成したマニュアルも継続的に改善していく必要があり、定期的な工数が発生する点も留意しておかなければなりません。
また、マニュアルに含まれていないことは対応しない従業員が現れる可能性があるなど、職場の柔軟性が欠如しやすくなる点もデメリットとして挙げられるでしょう。
マニュアルの作り方
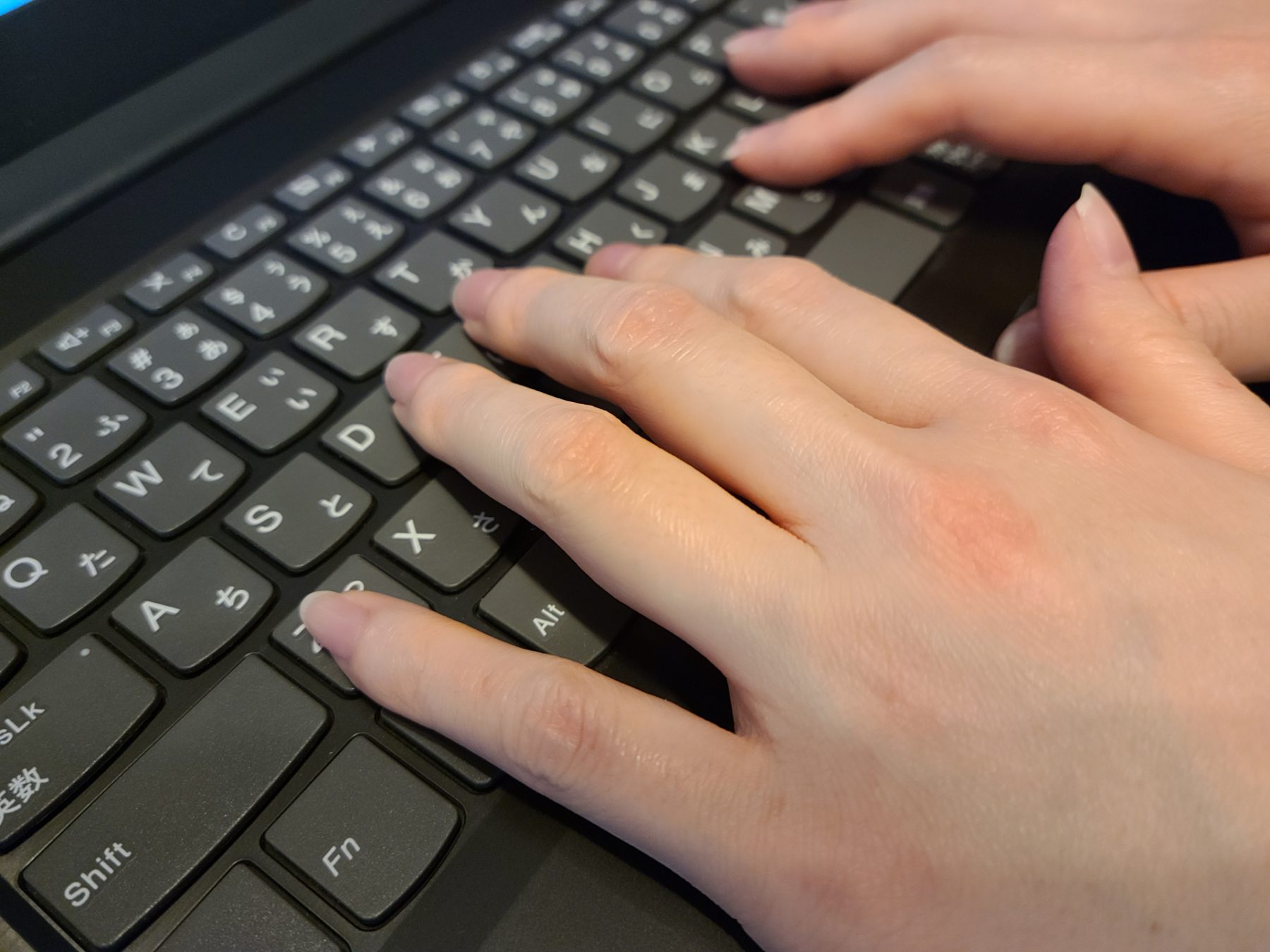
ここからはマニュアルの作り方について、4つのステップに分けてご紹介します。
ステップ①:現在の業務を洗い出す
マニュアルを作成する上で、まず行うのは現在の業務を洗い出す作業です。
マニュアルの対象となる業務について、具体的な項目や詳細な流れ、注意している点などを洗い出していきます。
同じ業務に従事している従業員全員に、どのような手順で業務を遂行しているかを箇条書きで洗い出してもらい、違いなども確認しながら漏れなく抽出しましょう。
ステップ②:抽出した業務を精査する
次に行うのは、抽出した業務の精査です。
先のステップで洗い出した業務について関係者間で共有しつつ、「その業務は本当に必要なのか」「足りていない業務はないか」といった観点で精査します。
精査するステップを挟むことで、マニュアル作成を通じて業務改善も実現できるため、必ず実施するようにしましょう。
ステップ③:マニュアルのフォーマットを作成する
業務精査と並行して、マニュアルのフォーマットを作成します。
マニュアルの基本的な項目としては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 業務遂行に必要な準備や前提条件
- 業務の詳細な作業手順
- 業務遂行の上で注意すべき事項
上記項目をベースとしつつ、現場従業員の意見や、企業として伝えたい内容などを踏まえ、マニュアルに盛り込む項目を定義しましょう。
ステップ④:フォーマットに記載する
最後に、フォーマットへ業務に関する詳細な情報を記載します。
ステップ①と②で洗い出して精査した内容を基に、マニュアルフォーマットの各項目を埋めていくことになるでしょう。
一通り記載が終わった後は、関係者間で内容の誤りや抜け漏れがないかをチェックし、必要に応じて修正します。
チェックの結果問題がなければ、マニュアルとしての体裁を整え、各従業員に配布したり、保管場所を通知したりしましょう。
マニュアルの作成・運用時のポイント

続いてマニュアルを作成・運用する際のポイントについてご紹介します。
マニュアルを作成する際のポイント
まずはマニュアルを作成する際のポイントを確認しましょう。
ポイント①:細部まで具体的に明文化する
一つ目のポイントは、細部まで具体的に明文化するという点です。
概要や大まかな手順しか記載されていないマニュアルでは、工数をかけて作成しても、結局使われることなく放置される可能性が高まります。
そのためマニュアルを作成する際は、実際に活用する従業員の視点に立ち、業務シーンを想定しながら細部に至るまで具体的に記述しましょう。
ポイント②:良い例と悪い例を記載する
次に挙げられるのは、良い例と悪い例を記載するという点です。
マニュアルに業務手順だけしか記載されていなければ、どの程度の水準で業務を遂行すべきかをイメージしにくいでしょう。
そのため業務における成果物や完成品などが明確にある場合は、良い事例と悪い事例を合わせて記載、あるいは完成図などを差し込むことが重要になります。
具体的な手順と具体例を合わせて記載すれば、従業員に明確なイメージを持ってもらえるでしょう。
ポイント③:業務の背景や目的を記載する
続いて挙げられるのは、業務背景や目的を記載するという点です。
どんな些細な業務であっても、それがプロセスに組み込まれている以上は、必ずその業務に取り組むべき背景や理由があるはずです。
そのためマニュアルを作成する際は、各業務の背景や目的なども併せて記載しておくことで、業務への意義やモチベーションを感じてもらいやすくなります。
背景や目的は、自社の価値観やビジョンをマニュアルに反映させる役割も果たすため、しっかりと網羅しておきましょう。
ポイント④:新人でもわかるように記載する
作成時のポイントとして最後に挙げられるのは、新人でもわかるように記載するという点です。
マニュアルはベテラン従業員よりも、経験の浅い従業員の方が参照する機会が多くなります。
そのため経験の浅い従業員や新人が読んでも意味がわかるように、専門用語を減らしたり、専門用語の説明を事前にしたりといった配慮が必要になるでしょう。
マニュアルを運用する際のポイント
マニュアル運用時のポイントも併せてご紹介します。
ポイント①:マニュアルを参照しやすい環境を作る
運用時のポイントとしてまず挙げられるのは、マニュアルを参照しやすい環境を作るという点です。
どれだけ作り込んだマニュアルでも参照されなければ意味がありません。
そのためマニュアル原本を現場に設置するだけでなく、社内ポータルサイトや業務アプリからでも参照できるようにするなど、アクセスしやすい環境の構築が重要になるでしょう。
ポイント②:マニュアル委員会を組織する
続いて挙げられるのは、マニュアル委員会を組織するという点です。
マニュアル運用に関する諸業務を取りまとめる委員会を組織することで、効率的かつ精度の高いマニュアル運用を実現できます。
例えば、マニュアルに関する従業員からの意見や要望を一元的に集約したり、マニュアルの改定内容に関するお知らせを実施したりといった取り組みができるでしょう。
ポイント③:定期的に改訂する
次に挙げられるポイントは、定期的に改定するという点です。
使われ続けるマニュアルにするには、常にマニュアルの鮮度を維持し、状況や業務の実態に即した状態にしておかなければなりません。
そのため、月一回など定期的に業務を振り返りながらマニュアルを精査する機会を設け、改定し続けることが重要になるでしょう。
ポイント④:顧客からの意見やクレームを反映させる
ポイントの最後にご紹介するのは、顧客からの意見やクレームを反映させるという点です。
マニュアルの改善や見直しをする際は、従業員からの要望だけでなく、顧客からの意見やクレームもしっかりと取り入れることがポイントになります。
内部と外部双方の意見を取り入れてマニュアルを改善し続けることで、効率的に業務品質の向上に繋げることが可能です。
マニュアルはアルバイトにとっても重要

マニュアルは、アルバイト従業員を定着させる上で重要な役割を果たします。
アルバイト従業員は正規の従業員と比べ、教育や研修が充実しているとは言えず、業務への理解が浅い状態で現場に投入されるケースも多いと言えます。
そういった状況においては、上司や先輩従業員から叱られることも多くなり、結果として早期離職してしまう可能性が高くなるでしょう。
しかし質の高いマニュアルが用意されていれば、アルバイト従業員の「何をすればいいかわからない」といった状況を打開することが可能です。
その結果、アルバイト従業員のモチベーションも高まり、早期離職するリスクを低減できるでしょう。
まとめ
今回はマニュアルの重要性や作り方などをまとめて解説してきましたが、いかがでしたか。
マニュアルは業務の属人化を防ぎ、各従業員の業務品質を安定化させる上で重要な役割を果たします。
従業員の教育は勿論、業務改善やインナーブランディングなどの活動にも活用できるため、あらゆる企業にとって役立つツールとなるでしょう。
ぜひこの記事を参考にマニュアル作成に取り組んでください。


