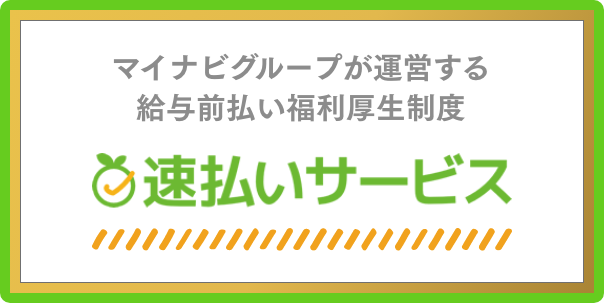近年、「スポットワーク」と呼ばれる、短時間または1日限定の仕事をする働き方が広がっています。人手不足の解消や柔軟な働き方の実現に寄与する一方で、契約成立のタイミングがわかりづらく、「無断欠勤された」「突然仕事をキャンセルされた」といったトラブルが起きているのも事実です。
企業と労働者の双方が安心してスポットワークを利用するためには、こうした背景を踏まえ、契約成立のタイミングや法的リスクについて正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、スポットワークにおける契約成立のタイミングについて解説します。政府による見解や対策についてもまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
スポットワーク契約の法的解釈

「スポットワーク」とは、継続した雇用関係がない状態において短時間または1日限定で仕事をする働き方を意味します。ほかに、「スキマバイト」や「単発バイト」とも呼ばれています。
スポットワークは、マッチング専用のアプリやサービスを通じて仕事を受発注するのが主流です。しかし、スポットワークに関する法律上の定義はありません。そのため、企業は活用にあたって、労働契約の成立や労働基準法の適用についてポイントを押さえておく必要があります。
労働契約の成立
スポットワークでは、基本的に企業と労働者の間に労働契約が成立します。
労働契約は使用者と労働者の合意があれば成立するため、書面による契約締結は必須ではありません。そのため、企業と労働者がアプリ上のメッセージなどで労働内容や勤務日時、報酬に合意していれば、労働契約が成立したとみなされます。
ただし、企業と労働者の間に指揮命令関係がない場合は、労働契約ではなく業務委託契約に該当します。それぞれの契約形態の主な違いは、下表の通りです。
| 契約形態 | 労働契約 | 業務委託契約 |
|---|---|---|
| 使用者と労働者の関係 | 雇用主と従業員 | 委託者と受託者 |
| 契約の目的 | 労働力の提供 | 業務の遂行成果物の納品 |
| 指揮命令 | あり | なし |
| 労働基準法の適用 | あり | なし |
スポットワークのような1回限りの仕事であっても、企業と労働者の間に指揮命令関係があれば、労働契約が成立すると覚えておきましょう。
労働基準法の適用と各種保険制度への対応
労働契約が成立すれば、たとえスポットワークであっても労働基準法の適用対象になります。そのため、企業がスポットワークを活用する場合は、労働時間の管理や労働者災害補償保険(労災保険)への対応などが求められます。
一方で、スポットワーカーのような短時間または1日限定で働く労働者は、基本的に雇用保険や社会保険の加入対象外です。スポットワークの利用にあたって、労働基準法などの労働関連法規に違反しないよう、以下のポイントを押さえておきましょう。
| 押さえておくべき項目 | 具体的なポイント |
|---|---|
| 労働時間の管理 | 労働者が異なる企業や事業所で働いている場合でも、労働時間を通算する必要がある労働時間が1日8時間を超える場合は、残業代の支払い義務が発生する |
| 労働者災害補償保険 (労災保険) | 仕事中の負傷や疾患は労災保険の適用対象になる契約成立のタイミング次第で通勤途中の負傷や疾患も労災保険の適用対象になる |
| 雇用保険 | 短時間または1日限定の働き方の場合は、原則として加入対象外になる |
| 社会保険 | 短時間または1日限定の働き方の場合は、原則として加入対象外になる |
| 守秘義務 | スポットワーカーが機密情報に接する可能性を考慮し、セキュリティ対策を講じる必要がある |
今後、スポットワークに関する制度の整備が進んでいく可能性も十分に考えられます。スポットワークを活用する際は、労働関連法規や関連する制度の動向についても把握しておきましょう。
関連記事:【スポットワーカー活用時の注意点】メリット・デメリットと併せて解説
スポットワークにおける契約成立のタイミング

ここからは、スポットワークにおける契約成立のタイミングについて見ていきましょう。
スポットワークは人手不足の解消や採用コストの削減に役立つ一方で、契約成立後に企業都合によるキャンセルをすると補償が発生する可能性がある点に注意が必要です。
【課題】企業による一方的なキャンセルなどの問題が発生
スポットワークの課題として、企業による一方的なキャンセルなどの問題が表面化している点が挙げられます。
企業と労働者はスポットワークのマッチングのために、専用のアプリやサービスを利用するのが一般的です。しかし、アプリやサービスによって契約成立のタイミングが異なり、企業と労働者の間で契約成立時期をめぐる誤解が生まれやすい状況にあるといえるでしょう。
2025年7月時点では、労働契約について「業務当日のチェックインが契約締結にあたる」「当日不採用になる可能性がある」としているサービスがあります。一方で、「採用・配置された時点で雇用契約が成立する」と明示しているサービスもあり、それぞれで見解が異なっている状況です。
【厚生労働省の見解】マッチング時点で労働契約が成立する
スポットワークで起きている企業による一方的なキャンセルなどの問題を受け、厚生労働省は2025年5月に「企業と労働者のマッチング時点で労働契約が成立する」との見解を明示しました。
今後より具体的な指針が成立すれば、スポットワークにおける労働者の権利保護が拡大すると期待されています。同時に、スポットワークを活用する企業は厚生労働省の指針に沿った社内ルールの整備が求められることになります。
【対策と方針】留意事項等をまとめたリーフレットの共有
スポットワークにおける契約成立のタイミングについて見解を示した後、厚生労働省は2025年7月に留意事項等をとりまとめたリーフレットを発行しました。関係団体等にリーフレットを共有し、周知を要請しています。
スポットワークを利用する労働者向け・事業主向けにそれぞれリーフレットが用意されており、トラブル防止のためには双方による理解が不可欠だといえるでしょう。事業者向けのパンフレットに明記されている労働契約締結時における注意点は、以下の3点です。
- 誰と誰が労働契約を締結するのかを確認すること
- 労働契約の成立時期を確認すること
- 労働契約成立後は労働基準法等を守ること
こうした一連の政府の動きを受け、なかには「労働契約成立タイミングは2025年9月に変更を予定している」との方針を明らかにしているサービスもあります。
参照:いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました。|厚生労働省
スポットワークにおける法的リスクを回避する方法

前述の通り、スポットワークの利用拡大に伴い、契約トラブルやキャンセル時の補償に関する問題が顕在化しています。企業がこうした法的リスクを回避するためには、厚生労働省の指針をもとに、契約内容や運用体制を整備することが大切です。
以下で、スポットワークにおける法的リスクを回避するための具体的な方法を解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
労務管理のポイントを理解する
スポットワーク利用時の法的リスクを回避するためには、厚生労働省が作成したリーフレットを参考に労務管理のポイントを理解することが大切です。リーフレットには、労働契約締結時における注意点のほか、休業時や賃金・労働に関する注意点などがまとめられています。
スポットワークにおける労務管理の主な注意点は、以下の通りです。
- 丸1日の休業または仕事の早上がりをさせる場合は、休業手当を支払う必要がある
- 着替えや掃除など、業務に必要な準備行為なども労働時間に該当する
- 一方的な賃金の減額は労働基準法違反になる
- 通勤途中または仕事中に怪我をした場合は、労働保険給付を受けられる
- 労働災害防止対策やハラスメント対策も事業主の義務である
労務管理のポイントを押さえ、適切な対応に努めましょう。
参照:「スポットワーク」を利用する事業主の皆さまへ|厚生労働省
契約成立の流れを明確化する
スポットワークにおける法的・金銭的リスクを回避するためは、「どの時点で契約が成立するのか」を明確に定義することが大切です。
厚生労働省のリーフレットには、一般的に「事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」と明記されています。
専用アプリやサービスを利用する場合は、契約成立のプロセスを正しく理解したうえで、利用規約や求人詳細ページ、通知メッセージなどを通じて労働者に責任範囲を明示するのがポイントです。企業と労働者の双方で認識のズレが起こらないような対応が、法的リスクの回避につながります。
参照:「スポットワーク」を利用する事業主の皆さまへ|厚生労働省
労働条件を明示する
雇用契約に基づくスポットワーカーを業務に従事させる場合、雇用主である企業は以下を含む労働条件の明示が義務付けられています。
- 賃金
- 労働時間
- 就業場所
- 業務内容 など
スポットワークは電子的な契約を交わすのが一般的です。この場合、専用のアプリやサービス内で労働条件を表示していれば、法的要件を満たすと考えられます。
ただし、トラブル発生時に労働者保護の観点から不利な立場に追い込まれないよう、企業独自の契約書を用意して正確な情報を明示しておくと安心です。
キャンセルポリシーを整備する
スポットワークにおける法的・金銭的リスクを回避するためには、キャンセルポリシーの整備も不可欠です。
スポットワークでは、企業都合か労働者都合かにかかわらず、直前または当日のキャンセルがトラブルに発展するケースが多くあります。そのため、キャンセル可能な期限を定めたり、状況に応じて一定のペナルティを科したりするなどして対応ルールを整備することが大切です。
キャンセルポリシーの整備は、自社を守るだけではなく労働者の安心な利用にもつながります。
補償体制を確立する
予期せぬトラブルに備えて事前に補償体制を構築しておくことも、リスク回避に役立つ方法の一つです。
スポットワークの利用にあたって、企業都合によるキャンセルをする可能性はゼロではありません。キャンセル時には、予定していた報酬の一部を補償金として支給する仕組みを事前に確立しておくことで、トラブルに発展するリスクを最小限に抑えられます。
通勤途中や仕事中の事故やトラブルに備えて確実に労災保険や損害保険に加入し、制度や補償範囲を書面にまとめて明確にしておくことも大切です。
まとめ
スポットワークは比較的新しい働き方であり、現時点では法整備が十分とはいえません。しかし、厚生労働省が指針を示しているように、今後は制度の整備が進み、ルールが明確化されていくことが期待されています。
スポットワークを活用する際は、企業と労働者の双方が安心して利用できるよう、契約成立のタイミングや契約形態を正しく理解して労務管理に努めましょう。
本記事では、スポットワークにおける契約成立のタイミングと、法的・金銭的リスクを回避するための具体的な対策について解説しました。ポイントをしっかり押さえて対応し、スポットワークを活用した柔軟な人材活用を実現してください。
<マイナビグループが運営する給与前払い福利厚生制度>