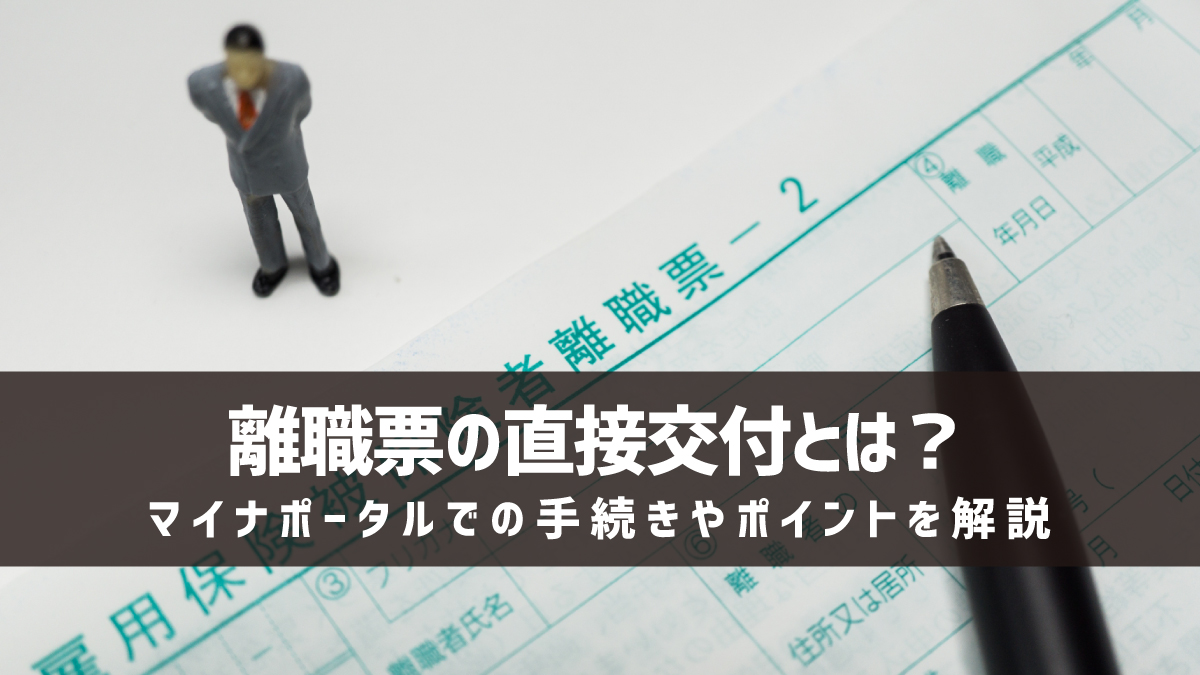離職票(離職証明書)は、雇用保険に加入していた従業員が退職した際に発行される書類です。少人数で人事労務を兼任している場合や、多くのパート・アルバイト従業員を雇用している場合など、離職票の交付手続きにかかる労力や時間を減らしたいと考える担当者も少なくないでしょう。
従来は事業主が紙で交付する方法が一般的でしたが、2025年1月20日からマイナポータルを通じてハローワークから直接離職者へ送付される新たな仕組みが導入されました。
本記事では、離職票の直接交付について、制度の概要や手続きの流れを解説します。メリットやデメリットもまとめているので、離職票の交付手続きを効率化したいと考えている方は、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
離職票の直接交付とは

離職票は、ハローワークから雇用保険に加入している従業員に対して交付される書類で、失業給付や年金・健康保険の手続きのために必要になります。2025年1月20日から、ハローワークが離職者のマイナポータルに離職票を直接送付する制度が開始され、手続きがよりスムーズになりました。
参照:2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!|厚生労働省
従来の交付手続き
従来の交付手続きでは、事業主が離職票を紙で手渡したり、離職者に郵送したりするのが一般的です。従来の交付手続きの流れは、以下の通りです。
- 事業主がハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を提出
- ハローワークが事業主へ「離職証明書(事業主控)」「離職票」を送付
- 事業主から離職者へ「離職票」を渡す
従来の手続きの場合は、常に事業主がハローワークと離職者の間に入って手続きを進める必要があります。また、離職者が離職票を受け取るために職場を訪れたり、担当者が郵送したりして手間がかかる点がデメリットだといえるでしょう。
【2025年1月以降】マイナポータルでの交付手続き
2025年1月20日以降は、一定の条件を満たした場合に限り、マイナポータルを通じてハローワークから離職者に直接離職票を交付できるようになりました。直接交付の大まかな流れは、以下の通りです。
- 事業主がハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を電子申請
- ハローワークが事業主へ「離職証明書(事業主控)」の電子データを送付
- ハローワークから離職者のマイナポータルへ「離職票」を直接交付
離職票の直接交付には一定の条件があるものの、企業にとっても交付手続きを簡略化できるメリットがあります。
離職票を直接交付するための3つの条件

マイナポータルを通じて離職票を直接交付するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 雇用保険被保険者番号とマイナンバーの紐づけ
- マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携
- 電子申請による資格喪失手続き
条件を満たさなければ、離職票の直接交付はできません。事業主と離職者双方による事前準備が必要になるため、制度の概要を理解して対応を進めましょう。
参照:2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!|厚生労働省
1.雇用保険被保険者番号とマイナンバーの紐づけ
マイナポータルを通じて離職票を直接交付するためには、離職者の「雇用保険被保険者番号」と「マイナンバー」を紐づける必要があります。雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐づいているかどうか確認する方法は、以下の2つです。
- 被保険者自身がマイナポータルの「わたしの情報」で確認する
- 事業主が被保険者全員の情報を確認する
雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐づいていない場合は、登録のために事業主からハローワークに「個人番号登録・変更届」を提出する必要があります。
2.マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携
離職票を直接交付を利用するための条件として、「マイナポータル」と「雇用保険WEBサービス」の連携が挙げられます。雇用保険WEBサービスを連携させると、マイナポータルで雇用保険に関する通知や手続き情報を受け取ることが可能です。
両サービスは、離職者自身に連携してもらう必要があるため、事業主として事前にアナウンスしておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
3.電子申請による資格喪失手続き
離職票を直接交付する条件として、電子申請による資格喪失手続きを行う必要があります。資格喪失届と離職証明書を紙で届け出る場合は、離職票の直接交付の対象にはなりません。
資格喪失手続きの書類は、e-Gov電子申請サービスを利用して提出しましょう。なお、離職票を直接交付するためには、社内の電子申請環境とあわせて運用体制の確立も不可欠です。
マイナポータルで離職票を直接交付する流れ
マイナポータルで離職票を直接交付する際は、以下の流れに沿って手続きを進める必要があります。
| 誰が | 具体的に何をするべきか | |
|---|---|---|
| 1.事前手続きをする | 離職者 | マイナンバーカードを取得するマイナポータルの利用手続きをする事業主を通じて、個人番号登録の手続きをする |
| 2.雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐づいているかを確認する | 離職者 | マイナポータルの「わたしの情報」から確認する |
| 3.マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させる | 離職者 | マイナポータルの「雇用保険WEBサービス」から「連携」を選択する |
| 4.電子申請する | 事業主 | 資格喪失届を作成する離職証明書を作成するe-Gov電子申請サービスから管轄先のハローワークに電子申請する |
| 5.マイナポータルで離職票を確認する | 離職者 | マイナポータルの「お知らせ」から交付状況を確認する交付のお知らせを確認したら、PDFファイルをダウンロードする |
なお、マイナポータルを通じて離職票が離職者本人に直接送付された場合、事業主へは離職証明書(事業主控え)のみが発行され、離職票は送付されません。また、直接交付においては、個人情報に該当するという理由から、事業主は離職区分コードを取得できないことになっています。
離職票を直接交付する場合は、従業員の協力も不可欠です。離職者に対してどのような案内をするべきか、事業主としてどのように手続きを踏むべきかといった点を理解したうえで、制度の導入を進めましょう。
離職票を直接交付するメリット

離職票の直接交付には、以下のようなメリットがあります。
- 作業の効率化
- 人的ミスの削減
- 紛失リスクの回避
- 郵送にかかるコスト削減
離職票を直接交付する場合は、電子データを取り扱うことになるため、郵送や手渡しする手間がなくなります。書類の紛失や誤送付といったリスクを減らせるほか、スピーディーな対応が可能になる点もメリットです。
離職者は退職後に担当者とやり取りする必要がなくなり、企業にとっては事務コストの削減につながります。離職票の直接交付は、利便性が高い制度だといえるでしょう。
離職票を直接交付するデメリット

離職票の直接交付には、以下のようなデメリットもあります。
- 事前準備が必要
- 従業員の協力が不可欠
- 対象外のケースあり
離職票を直接交付する際は、条件を満たすための事前の準備が不可欠です。マイナンバーの取得やマイナポータルの利用手続き、サービス連携など、制度を活用するためには、離職者の理解と協力が必要です。
従来の方法から直接交付に切り替える場合は、社内体制を整える必要もあります。条件を満たしていない場合は、従来通りの紙交付になるため、従業員によって手続き方法が異なるケースも考えられます。
メリットとデメリットの両方を理解したうえで、事業主・離職者の双方にとって利便性が高い方法を検討することが大切です。
マイナポータルで離職票を直接交付する際のポイント
ここでは、マイナポータルで離職票を直接交付する際のポイントを解説します。事前準備や注意点を理解していないと、離職者がスムーズに離職票を受け取れない可能性があるため気をつけましょう。
参照:マイナポータルを利用した離職票の受け取りFAQ|厚生労働省
資格喪失届にマイナンバーを記載した場合は対象外になる
資格喪失届に離職者のマイナンバーを直接記載して申請しても、離職票の直接交付の対象にはなりません。離職票を直接交付するためには、資格喪失届を提出する2週間程度前までに、マイナンバーの登録手続きを済ませておく必要があります。
この点を見落とすと、離職票の直接交付を利用できなくなるため注意が必要です。
お知らせ容量による送信エラーの可能性がある
離職票のPDFデータは、マイナポータルの「お知らせ」機能を通じて通知されます。しかし、マイナポータルのお知らせ容量が上限を超えていると、送信エラーになって離職票が届かないケースがあります。
お知らせ容量による送信エラーが発生した場合は、近くのハローワークの窓口で離職票を交付してもらうことが可能です。
マイナポータルで受け取った離職票は印刷の必要がない
直接交付された離職票は、電子データ(PDFファイル)としてそのまま利用できます。ハローワークの窓口で提示する際も、印刷せずにスマートフォンの画面上で表示するだけで問題ありません。
ただし、事業主が電子メールなどで送付した離職票のPDFファイルは、正式の電子交付とは異なるため、印刷して持参する必要があります。
5年間はマイナポータルで閲覧・ダウンロードできる
マイナポータルで直接交付された離職票は、交付日から5年間、「お知らせ」から閲覧とダウンロードが可能です。期間内であれば、必要なタイミングでアクセスできるため、各種手続きや再就職の際にも便利です。
また、保管の手間も省けるため、デジタル管理に慣れている方にとっては使い勝手が良い制度だといえるでしょう。
写しの交付も受けられる
マイナポータルで直接交付した離職票を誤って削除した場合は、近くのハローワークの窓口で写しを発行してもらえます。ハローワークの窓口で離職票の写しを交付してもらう場合は、免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
写しを交付してもらう際は、事前にハローワークに問い合わせて必要書類を確認しておくと安心です。
直接交付手続きは10日ほどかかる
離職票の直接交付手続きには、10日ほどかかります。直接交付の流れは、事業主が電子申請で離職手続きし、ハローワークで処理されると、離職票がマイナポータルに送信される仕組みです。
事業主による離職手続きの期限は、離職日の翌々日から10日以内とされています。事業主は離職者に交付までの日数を目安として伝えておくと、やり取りする手間を減らせるでしょう。
まとめ
マイナポータルを活用した離職票の直接交付は、2025年1月から導入された新しい制度です。従来の紙による離職票の交付手続きと比べて、業務の効率化や紛失リスクの低下などのメリットがあります。
ただし、離職票を直接交付するためには、「マイナンバーと雇用保険番号の紐づけ」「マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携」「電子申請での手続き」といった条件を満たす必要があり、事業主と離職者双方による準備が不可欠です。
本記事では、離職票の直接交付について、制度の概要や手続きの流れを解説しました。事前準備と従業員への周知を図ることで、スムーズな離職票の交付を実現できるでしょう。

人材不足をアルムナイで解決しませんか?
深刻な人材不足に退職者との”つながり”が効く
在職中から退職後まで、一貫した関係構築で退職スタッフの “再戦力化” をサポート!