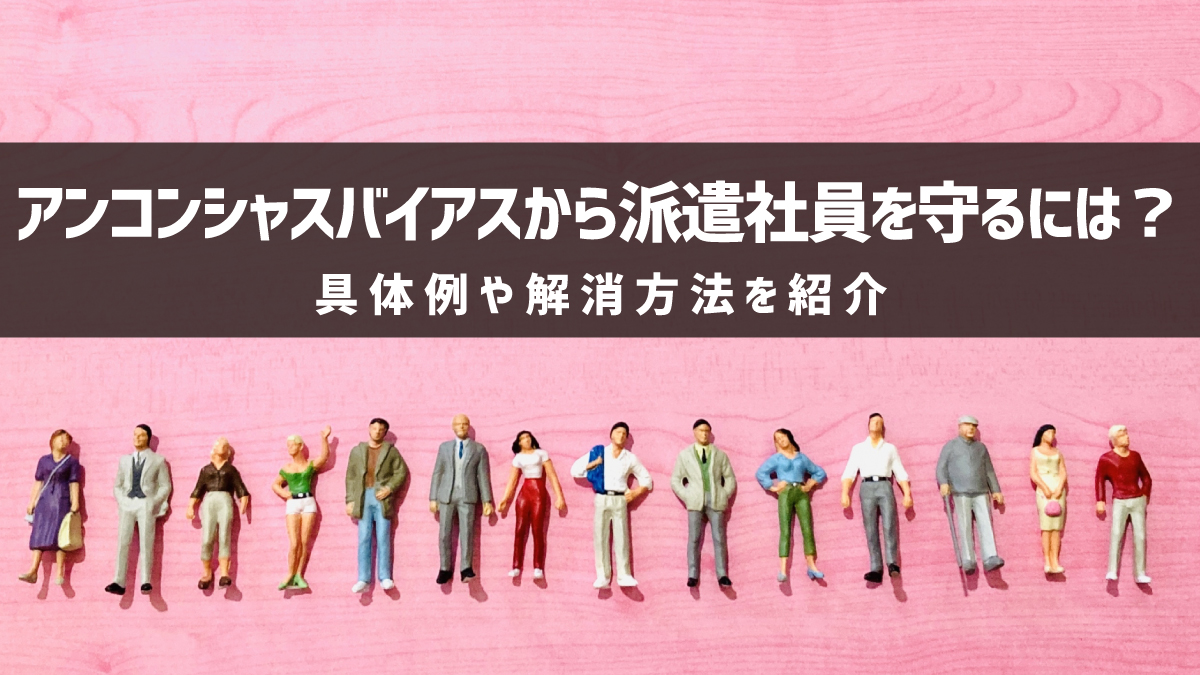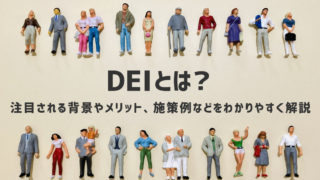近年、ダイバーシティやインクルージョンといった「共創」の考え方が広がるなか、職場に存在する「アンコンシャスバイアス」に対する問題意識が高まっています。
アンコンシャスバイアスとは、無意識の偏見や思い込みを意味する言葉です。特に、派遣社員は雇用形態の違いからアンコンシャスバイアスの対象になりやすく、職場定着やキャリア形成に影響を及ぼすケースもあります。
本記事では、派遣社員に対するアンコンシャスバイアスの具体例や解消方法を紹介します。社員の行動変容につながる対策を実施したいとお考えの方は、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
アンコンシャスバイアスとは

アンコンシャスバイアスとは、性別や年齢、人種、経験など、さまざまな要素に起因する無意識の偏見や思い込みのことです。このような先入観は、本人が自覚していなくても、日常の行動や判断に影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、「若いから責任ある仕事はまだ早い」「派遣社員には重要業務を任せられない」といった思い込みが、差別的な言動や不公平な評価につながるケースもあるでしょう。
アンコンシャスバイアスは誰にでもあるものです。そのため、アンコンシャスバイアスそのものが悪いわけではありません。企業にとって大切なのは、その存在に気づいて適切に対処していくことです。
【具体例】派遣社員に対するアンコンシャスバイアス

派遣社員は雇用形態の違いから偏見の目を向けられやすく、さまざまな場面でハラスメントにつながっている可能性があります。以下は、職場の各場面で見られる代表的なアンコンシャスバイアスの例です。
| 場面 | 具体例 |
|---|---|
| 職場環境 | 派遣社員を「派遣さん」と呼ぶお茶出しや電話取り次ぎなど雑務ばかり任せる意思決定の場に参加させない |
| 採用 | 正社員登用を希望する派遣社員に過剰なハードルを設ける派遣社員は正社員になる能力が不足していると決めつける |
| 育成 | シニア世代の派遣社員はパソコンを使いこなせないと決めつける派遣社員には責任ある業務を任せない |
| 人材活用 | 派遣社員は昇給・昇進させる必要がないと考える大きな商談は正社員に任せるべきと決めつける |
このような偏見や思い込みは、派遣社員のモチベーションを下げるだけでなく、職場全体の活力やチームワークにも悪影響を及ぼします。
アンコンシャスバイアスの種類

アンコンシャスバイアスにはさまざまな種類があります。派遣社員の立場を守るためにも、まずはどのようなバイアスが存在するのかを理解しておくことが大切です。
アインシュテルング効果
アインシュテルング効果とは、慣れ親しんだ視点や考え方に固執し、新しい発想を無視してしまう心理傾向を意味します。
人は過去の成功体験に基づいた方法を優先しやすく、慣れ親しんだやり方に固執しがちです。その結果、革新的なアイデアや外部からの提案を軽視してしまうことがあります。職場環境においてアインシュテルング効果が作用すると、視点が偏ったり新しいイノベーションが生まれなくなったりするなどの弊害につながります。
確証バイアス
確証バイアスとは、自分が考えや価値観に合致する情報ばかりを集め、都合の悪い情報を無視してしまう心理傾向です。
人は自分の信念を裏付ける情報を集めることで安心感を得ようとします。しかし、確証バイアスが作用して客観的かつ実証的な事実を否定するようになると、誤った意思決定をしてしまう恐れがある点に注意が必要です。
ステレオタイプバイアス
ステレオタイプバイアスとは、性別や年齢、人種、経験といった属性による固定的なイメージで相手の特性を判断してしまう心理傾向を意味します。
人は情報を素早く整理しようとして物事を属性ごとに分類して考えがちです。ステレオタイプバイアスが作用すると、不適切な発言や態度を引き起こすだけではなく、誤った判断につながる可能性があります。
慈悲的差別
慈悲的差別とは、一見すると好意的な配慮に見える行動を通して、無意識のうちに相手を下に見て扱ってしまうことです。
たとえば、「助けてあげる」という配慮の姿勢は、相手の能力を過小評価していることを前提としているケースがほとんどです。職場においても、慈悲的差別は他者の挑戦機会を奪ったり、かえって相手を傷つけたりする恐れがあります。
ハロー効果
ハロー効果とは、ある目立った一つの特徴が全体の評価に過度な影響を与えてしまう現象です。
ハロー効果が作用すると、優れた特徴によって評価が過大になる場合もあれば、ネガティブな特徴のせいで過小評価につながるケースもあります。職場においてハロー効果がネガティブに作用すると、相手の本質を見極める妨げになり、人事評価を誤るリスクが生じます。
集団同調性バイアス
集団同調性バイアスは、多数派の意見に合わせようとするあまり、自分の意見や考え方を抑えて物事を判断してしまう心理傾向です。
集団から孤立することを避けたいという心理傾向によって、集団同調性バイアスが生じます。職場において集団同調性バイアスが作用すると、少数派の意見が軽視されて多様な視点が失われるだけでなく、イノベーションが生まれにくくなります。
権威バイアス
権威バイアスとは、役員や上司、専門家といった権威ある人物の意見を盲目的に受け入れてしまう心理傾向です。
人は地位や肩書のある人物を無意識に信頼し、その人の意見を正しいと判断する傾向があります。しかし、権威ある人物によって社員一人ひとりの意見が左右されるようになると、企業は革新の機会を失うことになるため注意が必要です。
派遣社員はアンコンシャスバイアスの影響を受けやすい

派遣社員は、雇用形態の違いから正社員と比較されやすく、アンコンシャスバイアスの影響を強く受ける立場にあります。雇用形態による先入観が、無意識のうちに派遣社員の評価や業務分担に影響を与えるからです。
派遣社員が成果を出しても正社員と比べて過小評価されたり、業務分担の際に補助的な役割に回されたりするケースなどが一例です。公平な職場づくりのためには、派遣社員だからといって区別することなく、自社の社員と同様に接するよう組織全体で取り組んでいく必要があります。
派遣社員に対するアンコンシャスバイアスを解消すべき理由
派遣社員に対するアンコンシャスバイアスは、企業と個人の双方に悪影響を及ぼすため、できるだけ早く解消すべきです。派遣社員に対するアンコンシャスバイアスが存在すると、具体的に以下のような問題につながります。
- ハラスメント行為が常態化する
- 派遣社員のキャリア形成が妨げられる
- モチベーションの低下により業績が悪化する
- 多様性が失われてイノベーションが生まれにくくなる
- 優秀な人材が流出する
- 企業のイメージや信頼性が損なわれる
職場でハラスメント行為が常態化すると、従業員のモチベーションや生産性が低下し、業績悪化につながるリスクがあります。また、多様性が失われることでイノベーションが停滞すると、企業は成長機会を失ってしまうでしょう。
これらのリスクを防ぎ、健全な職場環境を維持するためには、派遣社員に対するアンコンシャスバイアスを解消する必要があります。
関連記事:DEIとは?注目される背景やメリット、施策例などをわかりやすく解説
派遣社員に対するアンコンシャスバイアスの解消方法

アンコンシャスバイアスは誰にでもあるため、意識的に取り組まなければ解消は困難です。組織として具体的な対策に取り組むことが、派遣社員を含むすべての従業員が公平に活躍できる職場づくりにつながります。
以下で、派遣社員に対するアンコンシャスバイアスの解消方法を紹介するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
チェックリストを用いて現状を把握する
アンコンシャスバイアスを解消するために、まずは職場や社員一人ひとりにどのような偏見があるかを認識する必要があります。すでに存在している無意識の偏見に気づいていない状態では、具体的な改善策を立てられません。
派遣社員に対するアンコンシャスバイアスを把握するためには、チェックリストを活用したり、アンケートやヒアリングを実施したりする方法がおすすめです。派遣社員に特化した内容ではありませんが、厚生労働省や内閣府男女共同参画局、自治体などのWebサイトで公開されているチェックリストを参考にするとよいでしょう。
現状を正しく把握することで、効果的な改善策を検討しやすくなります。
体験型研修を実施して対話の場を設ける
公平な職場づくりのためには、アンコンシャスバイアスに関する学びに加えて、対話の機会を設けましょう。正社員と派遣社員が互いの立場や考えを理解し、無意識の偏見に気づくことが、行動変容につながるからです。
実際に、アンコンシャスバイアスの研修を実施したにもかかわらず、社員の行動変容につながっていないケースもあるでしょう。
この場合、ロールプレイやケーススタディを取り入れた体験型研修を行うと、正社員と派遣社員が互いの立場に立って物事を考えるきっかけになります。対話を重ねて職場全体の理解を深めることが、アンコンシャスバイアスの解消につながるでしょう。
派遣社員を意思決定の場に参加させる
派遣社員を意思決定の場に参加させることも、アンコンシャスバイアスを解消する対策の一つです。派遣社員を単なる補助的な労働力ではなく、組織の一員として尊重することがアンコンシャスバイアスの解消につながります。
部署やチーム内の意思決定の場に派遣社員を参加させるうちに、誰もが公平に能力を発揮できる環境が整い、本人たちも自己効力感を持って働けるようになります。その結果、職場における「補助的な存在」「能力不足」といった先入観もなくなっていくでしょう。
まとめ
アンコンシャスバイアスはどの職場にも存在します。しかし、たとえ悪意のない言動であってもハラスメントにつながる可能性があるため注意が必要です。多様な人材が集まる職場では、派遣社員がその影響を受けやすく、評価やキャリア形成に不公平が生じるリスクもあります。
アンコンシャスバイアスから派遣社員の立場を守るため、企業はチェックリストを活用して現状把握に努めたり研修を実施したりして、社員一人ひとりの行動変容を促すことが大切です。派遣社員を活用して効果的な人材戦略を展開できるよう、アンコンシャスバイアスの解消に取り組みましょう。