2025年4月から、新たに「育児時短就業給付金」と「出生後休業支援給付金」の2つの制度が設けられました。派遣社員やアルバイトなどにも適用されるため、非正規労働者を抱える企業にとっては人材定着や採用競争力の強化につながる効果が期待できるでしょう。
本記事では、派遣社員やアルバイトに対する育児給付金の一覧や適用条件を解説します。非正規労働者が育児給付金を受け取る企業側のメリット・デメリットや、運用体制づくりのポイントも解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
派遣・アルバイトも育児給付金の給付対象になる

派遣社員やアルバイトなどの非正規労働者も、一定の条件を満たせば、育児給付金制度の対象になります。
2022年4月に有期雇用労働者の取得要件が緩和され、派遣社員やアルバイトでも、「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない」場合には、権利として育児休業の取得が認められています。
参照:有期雇用労働者の育児休業や介護休業について|厚生労働省
育児給付金・手当の一覧と適用条件
2025年7月時点で、派遣社員やアルバイトも給付対象になる育児関連の給付金および手当は、下表の通りです。
| 給付金・手当 | 内容 | 支給額 | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 出産時に手当金を支給 | 一児の出産につき50万円 | 公的医療保険の加入者 |
| 出産手当金 | 産前産後休業中の収入を補填 | 標準報酬日額の3分の2相当 | 健康保険の被保険者 |
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生時育児休業)中の収入を補填 | 賃金日額×67%相当 | 雇用保険の被保険者 |
| 育児休業給付金 | 育児休業期間中の収入を補填 | 賃金日額×67%相当 | 雇用保険の被保険者 |
| 育児時短就業給付金 | 短時間勤務による収入減を補填 | 育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当 | 雇用保険の被保険者 |
| 出生後休業支援給付金 | 両親がともに育児休業を取得した場合に上乗せ支給 | 賃金日額×13%相当 | 雇用保険の被保険者 |
この中で、「育児時短就業給付金」と「出生後休業支援給付金」が、2025年4月から新たに設けられた制度です。次項より、新たな給付金制度の概要について詳しく解説します。
【2025年改正】育児時短就業給付金
2025年4月から新たに設けられた「育児時短就業給付金」は、派遣社員やアルバイトを含めた労働者が、育児と就業を両立するための後押しになる制度です。
育児時短就業給付金とは
育児時短就業給付金とは、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金のことです。
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。なお、2025年7月31日までの支給限度額は459,000円で、以後毎年8月1日に改定が予定されています。
参照:2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します|厚生労働省
育児時短就業給付金の適用条件
派遣社員やアルバイトなどの非正規労働者でも、一定の要件を満たせば育児時短就業給付金の給付対象になります。育児時短就業給付金を受け取れるのは、以下の2つの要件をどちらも満たす方です。
- 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
加えて、給付金は、以下の要件をすべて満たす月について支給されます。
- 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
- 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
育児時短就業給付の対象になるのは、2歳未満の子どもを育てながら短時間勤務で働く方に限られます。この制度により、子育て中の派遣社員やアルバイトが柔軟な働き方を選択しやすくなるでしょう。
【2025年改正】出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」は、男性の育児休業取得率が女性と比べて依然として低い状況のなか、共働き・共育てを推進するための制度として新たに創設されました。
出生後休業支援給付金とは
出生後休業支援給付金とは、子どもが生まれたあとに、父母の両方がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合に支給される給付金のことです。配偶者がいない場合は、単独の保護者が受給対象です。出生後休業支給給付金の支給額は、以下のとおり算出されます。
| 支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13% |
この制度は、出生時育児休業給付金や育児休業給付金と併用できるため、共働き家庭における経済的負担のさらなる軽減が期待できます。
参照:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します|厚生労働省
出生後休業支援給付金の適用条件
派遣社員やアルバイトなどの非正規労働者であっても、以下の要件を満たすことで出生後休業支援給付金の対象となります。
- 被保険者および配偶者(または単独の保護者)がそれぞれ14日以上の育児休業を取得したこと
- 被保険者の配偶者が、子の出生後8週間を経過する日の翌日までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと
なお、以下のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受けて別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業やフリーランスなど、雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
支給対象となる期間は、子の出生後8週間以内です。つまり、出産後すぐの育児休業取得が前提となるため、計画的に準備を進める必要があります。
派遣・アルバイトが育児給付金を受け取るメリット

派遣社員やアルバイトが育児給付金を受け取ることで、企業側にも以下のようなメリットがあります。
- 離職防止につながる
- 労働力を確保できる
- 企業イメージを向上できる
- ハラスメントの防止につながる
非正規労働者が育児給付金制度を活用すると、育児中のスタッフの経済的不安が軽減され、離職防止につながる点が大きなメリットです。職場への定着率が向上して人材流出を防げるようになると、企業は安定した人材体制を維持しやすくなります。
また、育児支援への取り組みを通じて正規・非正規労働者間の差別がなくなると、派遣社員やアルバイトの満足度向上やモチベーションの維持につながるでしょう。その結果、対外的な評価が高まる効果も期待できます。
派遣・アルバイトが育児給付金を受け取るデメリット

派遣社員やアルバイトなどの非正規労働者に育児給付金制度を適用する場合、企業側にはデメリットもあります。主なデメリットは、以下の通りです。
- 勤務調整やシフトへの影響が懸念される
- 給付申請手続きに手間がかかる
- 制度理解の促進にコストがかかる
特に、シフト制の現場では、育児休業や短時間勤務制度の取得によって人員の再配置や勤務割の調整が必要になります。そのため、業務運営に一時的な混乱が生じる可能性もあるでしょう。
さらに、社内で制度について正しい理解を浸透させるためには、非正規労働者に対する丁寧な説明が求められます。これにより、人事担当者の業務負担が増えるケースも考えられます。
しかし、これらの対応は長期的な人材確保につながる投資ともいえるでしょう。
派遣・アルバイトに対する育児給付金の運用体制づくり
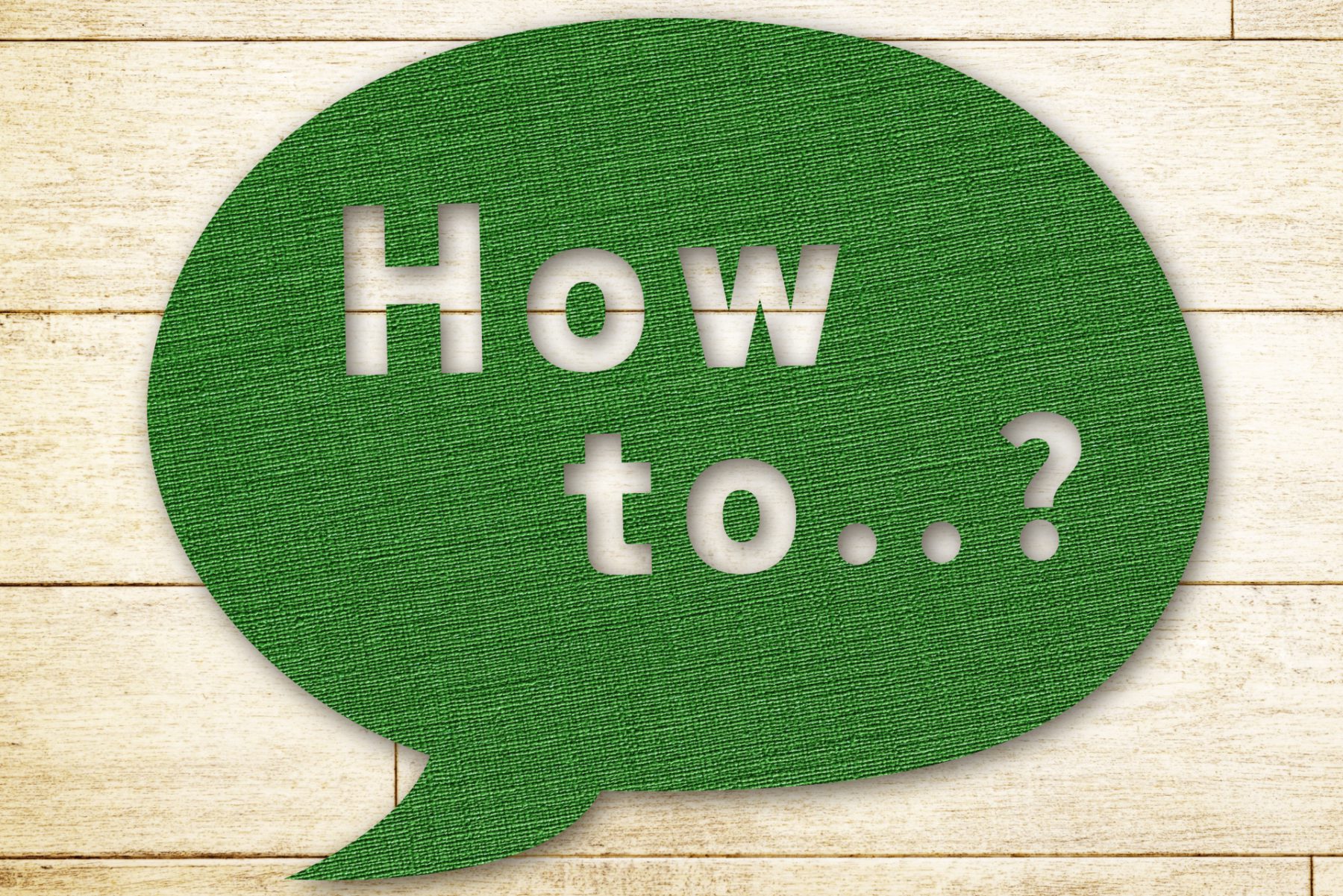
多くの派遣社員やアルバイトを雇用する企業にとって、2025年4月から新設された育児給付金の制度活用は、人材確保の面で大きなチャンスになります。ただし、育児給付金制度を戦略的に活用するためには、運用体制の整備が不可欠です。
以下で、制度活用に向けた運用体制づくりのポイントを解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
就業規則への明記
育児給付金制度の運用については、派遣社員やアルバイト向けの就業規則に明記する必要があります。明文化されていないと、対象者が有する権利について正しく把握できず、制度の活用が進まない恐れがあるためです。
育児給付金の取得要件や申請の流れ、取得後の復職に関する対応などを具体的に記載しておけば、トラブル防止にも役立ちます。特に、人材派遣会社の場合、派遣元と派遣先の双方による規定整備が求められるほか、契約内容との整合性も重要になります。
就業規則を見直す際は、必要に応じて社会保険労務士などの専門家と連携し、実効性のある規定を定めましょう。
雇用環境の整備
育児給付金制度の実現性を高めるためには、取得しやすい雇用環境の整備が不可欠です。給付金制度を利用できるとわかっていても、取得しづらい雰囲気であれば活用にはつながりません。
派遣社員やアルバイトによる育児休暇の取得を後押しするためには、具体的に以下のような取り組みが必要です。
- 業務代替要員の確保
- 復職後の配置転換
- 復職後の業務内容の調整
- フォロー体制の明確化
特に、シフト制の現場では、育児休業や短時間勤務制度の取得者が出た場合の対応力が、制度運用の実現性を左右します。給付金制度を円滑に運用するためにも、柔軟な人員配置が可能な体制を整えることが大切です。
ハラスメント対策の強化
派遣社員やアルバイトに安心して育児給付金制度を利用してもらうためには、ハラスメント対策も重要です。育児休業の取得や給付金の申請に関して、派遣社員やアルバイトが不利益を受けたり、周囲からの圧力を感じたりすることがないようにしましょう。
具体的には、相談窓口を設置するほか、管理職に法令遵守の重要性を教育したり多様な働き方への理解を社内に浸透させたりすることも大切です。誰もが安心して制度を利用できるよう、ハラスメント対策の強化に努めましょう。
スタッフへの正確な情報提供
育児給付金制度の適切な運用のためには、スタッフに正しく情報を提供する必要があります。
たとえ雇用環境が整っても、派遣社員やアルバイトが育児給付金の制度や申請方法を知らなければ活用にはつながりません。つまり、単純に体制を整えて就業規則に明記するだけでは不十分だといえます。
具体的には、社内報やポスター、説明会などを通して制度の周知を図るのがポイントです。特に、派遣社員やアルバイトなどの非正規労働者は情報へのアクセスが限定される傾向にあります。そのため、人事担当者から個別に案内してフォローするとよいでしょう。
まとめ
2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」と「出生後休業支援給付金」の2つの制度は、派遣社員やアルバイトを含めた非正規労働者にも適用されます。これにより、育児と就労の両立が今後ますます現実的な選択肢となっていくといえるでしょう。
一方で、企業には制度を正しく理解し、派遣社員やアルバイトのために実効性のある運用体制を整える責任が生じます。就業規則の見直しや雇用環境の整備を図ったり、スタッフに正確な情報を提供したりして、育児休業の取得を後押しできる体制づくりを進めることがポイントです。
本記事では、派遣社員やアルバイトに対する育児給付金制度についてまとめました。制度の活用を前提とした多様な働き方を企業文化に組み込んでいくことで、採用競争力の強化につなげましょう。
アルバイト・パート・派遣スタッフ向けマイページアプリ

就業規則・労使協定など社内周知をスムーズに!
貴社専用のスタッフマイページを管理画面から簡単に作成できます。メニューアイコンも事業所ごとに出し分けたりと自由自在。
貴社のスタッフはアプリをインストールしたら本人認証するだけで、社内のさまざまな情報やツールにアクセスできます。
さあ、貴社のDXの第一歩をはじめましょう。



